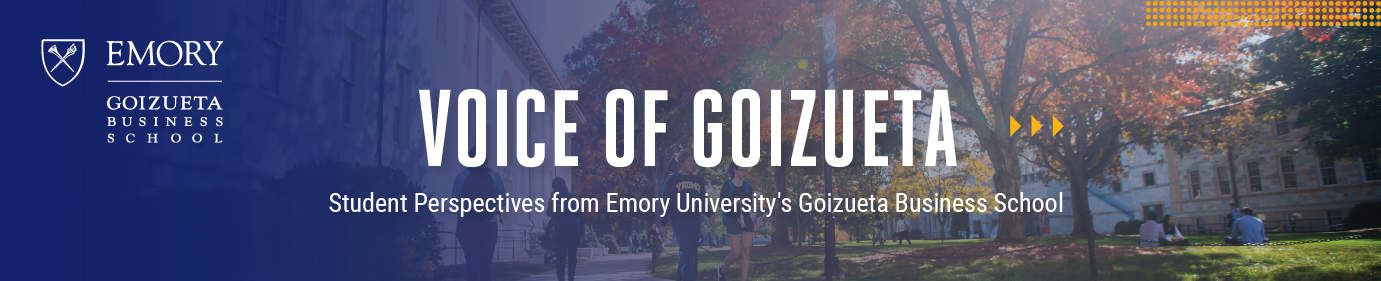教室の壁を越えることで、学問に命を吹き込むことができる

高校生の頃、私は数学に愛憎を抱いていました。 代数学は見事に合格し、方程式の中の「x」変数を解くというチャレンジにオタク的な楽しみを見いだしました。 幾何学は、ピタゴラスの定理の基本さえつかめば、それほど複雑ではありませんでした。 しかし、微積分は……ああ、恐ろしい微積分だ。 微積分は、私の頭では理解できなかったんです。 だから、勉強が好きでかなり強い生徒だった私も、微積分を扱うたびに別人のようになった。 私は、微積分の教科書とにらめっこしながら、長年にわたって多くの教師や親が聞いてきた言葉を繰り返し唱え、いらいらした夜を過ごしたことを覚えています。”いつになったらこれを使うんだ!”
微積分の実戦的な応用が理解できなかったので、学ぶ意欲があまりなかったのです。 私の代数学の教科書には、ある時間内に到着するために必要な車の速度を測定したり、希望する利益率を考慮して製品の価格を決定したりと、実世界での応用例が無数に紹介されていました。 同様に、私の幾何学の宿題は、建設プロジェクトのための寸法計算など、常に実社会の問題を参照するものでした。 でも、高校の微積分の宿題は、現実世界とは関係ない数学の問題を解かせるだけでした。 大学の経済学部に入ると、微積分の具体的な応用がようやく理解できるようになり、この科目がそれほど怖くなくなったのです。 それ以来、理解できないときは、実生活に結びつければいいのだと思うようになりました。
ゴイズエタでは、ビジネススクールの教えを実社会に適用するために、あまり苦労することはありませんでした。 ゴイズエタでは、ビジネスを真空状態で学ぶことはありません。 むしろ、教授陣は常に理論と実践を結びつけているのです。 このギャップを埋める方法の一つが、シミュレーションです。これは、ビジネス上の意思決定を行い、その決定が売上、利益、株価などの指標にどのように影響するかを即座にフィードバックする対話型の学習体験です。 このギャップを埋めるもう一つの方法は、クラスでの議論に貢献するために、自分の本業での逸話を共有することです。
この夏、管理会計の授業で、理論と実践を結びつけた授業があったのですが、その中でも特に印象に残っているのが、この授業です。 カレン・セダトール教授は、私たちの多くが会計の分野でキャリアを積むことを計画していないにもかかわらず、ビジネスリーダーにとって管理会計の基本的な理解がいかに重要であるかを理解してほしいと考えています。 そのため、勤務先の経理担当者にインタビューを行い、それぞれの会社で管理会計がどのように機能しているかを振り返るジャーナルを書くことが主な課題の1つでした。
最初は会社の会計の世界を掘り下げることに抵抗がありましたが、日記の練習はとても役に立つ経験でした。 日記の答えを探すうちに、新しい同僚と部門を超えた関係を築くように促されました。 この仕事がなければ、おそらくほとんど交流のなかったであろう2人の経理担当の同僚を昼食に誘った。 その後2時間、固定費と変動費、オペレーティング・レバレッジ、業績評価などについて話し合いましたが、会計は単なる予算編成や数字の計算以上のものであることを実感しました。 管理会計は、企業の戦略的方向性に影響を与える重要な役割を担っている。
教室の壁を越えるだけで、コースに命が吹き込まれることもあるのです。 10年後、管理会計の講義の内容は忘れても、会計の考え方が実感できる昼食は忘れないと思います。
卒業まで待たなくても、ビジネススクールで学んだことを実社会で活かせるのはありがたいことです。 現実の世界は、すでにゴイゼッタの経験の中に深く刻み込まれているのです。